材木座の鎮守とされるのが五所神社です。材木座の村人の守ってきた村社でもあったところで、6月の例大祭は二基の神輿が海上渡御することで知られているだけでなく、貴重な石造物が境内に残されており、民間信仰の生きている感じがします。
- 祭神
大山祇命・天照大御神・素戔嗚尊・建御名方命・崇徳院霊の五柱 - 鎌倉市材木座2-9-2
- 行き方
鎌倉駅東口バスロータリー
九品寺循環 五所神社前下車 徒歩1分 - ホームページ 五所神社
材木座の旧村社

1888(明治21)年に乱橋村と材木座村をの合併して乱橋材木座村となりましたが、そのころは乱橋に三島社と八雲社、材木座に諏訪社、金比羅社、見目社の五社がありました。1906(明治39)年、明治政府(内務省)が全国の一村に一社とする神社統合令を出したことにより、1908(明治41)年に五社が合併して造られたのが五所神社です。村名も材木座村となり、五所神社は村社と社格が定められました。
関東大震災の山崩れで社殿が倒壊、埋没するという災害がありましたが、昭和6年7月に再建されました。現在は社格制度はなくなり村社とは言われませんが、鳥居前の標識には今も村社の文字が残っています。


参道を進み、石段を登ると左手に社務所らしき建物があり、さらに一段上がった所の左手が社殿です。お詣りを終えて境内を見渡すと、御神輿が三基並ぶ収蔵庫目につくほか、沢山の庚申塔などの石造物が並んでいることに驚くでしょう。


江戸時代の神輿


三基の神輿の中の、右の一基は江戸末期の弘化4(1847)年に製造されたもので、鎌倉市の指定有形文化財とされています。右手の説明板によると、「この神輿はもと材木座村の鎮守であった諏訪社のものとして作れましたもので、内部に残る銘文から、江戸時代後期の弘化4年(1847)に、光明寺門前の大工と、扇ヶ谷の仏師によって造られたことが分かります。他の神輿と比べて規模が大きく、江戸時代後期の建築形式が整っており、建造後に2度の修理を経ていますが、今も制作した当時の姿をよくとどめています。」とのことです。


左は2018年6月12日に朝日アウトドアの皆さんと訪ねたとき、数日前の例大祭の後始末をしていた方が、丁寧に説明していただきました。右は2025年6月8日、例大祭で三基の神輿が出払ったあとのがらんとした様子。
天王唄
この三基の神輿は、例年6月8日に行われる例大祭で、材木座海岸での海上御渡りする神輿です。
例大祭で、御神輿の担ぎ手たちが唄うのが「天王唄」です。

真ん中の神輿の上の天井に、祭で唄われる「天王唄」の歌詞が書かれています。
諏訪社が五所神社以前の材木座村の社です。たしかに神輿の上に八咫烏が羽ばたいています。
「和賀」とは和賀江島のことで、鎌倉時代に築かれた港でした。
天王唄
宮を朝出て
八丁を廻る アーラヨイ
八丁の氏子は ヤレコラ
出て拝む オモシロヤ
来たらごらんよ
諏訪社の神輿 アーラヨイ
八咫鏡に ヤレコラ
八咫烏 オモシロヤ
金比羅さんに
燈火がともる アーラヨイ
和賀に出入りの ヤレコラ
舟しるべ オモシロヤ
弘長2(1262)年銘の板碑

神輿庫の右手に小さな小屋に納まった板碑があります。これは鎌倉時代の弘長2(1262)年という製造年が彫られている、貴重な文化財です。まさに鎌倉時代の「物」がここに残されているのです。

鎌倉時代の板碑で完全な形で現存する貴重な遺物で、1941(昭和16)年には国の重要文化財(現在は鎌倉市の指定文化財)とされています。かつては材木座の感応寺(真言宗、現在の材木座公会堂一帯)にありましたが廃寺となったためこの地に遷されました。
石質は黒色粘板岩、中央に剣に巻き付いた龍になぞらえた大日如来をあらわす種子「バン」が彫られ、「大日変じて不動となる」の意を表現しているといいます。
板碑とは故人の追善や供養のための板状の石碑で、鎌倉時代にたくさん作られましたが、五所神社の板碑はほぼ完全に残った貴重なものです。材木座の光明寺の大殿右脇にも同じような板碑があり、もとはペアであったと考えられています。
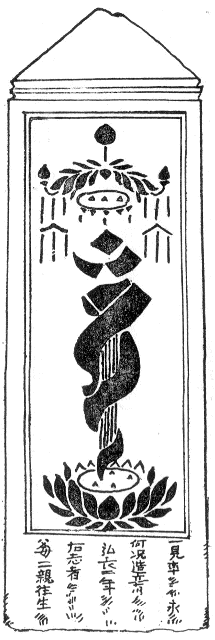
庚申塔の数々

五所神社で驚くことは、境内に並べられた庚申塔の多さです。これらはもともと境内にあったのではなく、神社が統合される前の町内の聚落ごとに造られ、バラバラだった物が、明治以降、社が五所神社に統合されたこと、都市化が進んで道路工事によって庚申塔が邪魔にされたこと、などの理由によって、ここ一カ所に集められた結果です。
全部で10数体もあり、そのすべてを紹介することはできませんが、興味深い物をいくつか取り上げてみましょう。

唐破風付笠塔婆
正面に阿弥陀如来と下辺にきかざる
右側面に乱橋講中十七人、下にいわざる
左側面に天和4年仲春廿四、下に見ざる
天和4年は1684年

舟形
上辺に日月、中央に「奉造立帝釈天王」と刻み、両脇に牡鶏・牝鶏、右に現世安穏、左に後生全書
下に三猿
寛文12年の造立

Episode キリシタンの像?
石段の左手の庚申塔の右端に、背後に十字架の立っている小さな石像があります。よく見ると女の子が後ろ手に縛られています。
社務所の方のはなしではいつ頃からかわからないがここに置かれるようになり、「お春さん」といわれているそうです。その姿から隠れキリシタンの像だと考えられ、十字架が添えられました。
左の石碑は馬頭観音。
樹木と花
・社殿右のタイサンボク



あまり目立ちませんが社殿と神輿庫の間に、大きなタイサンボクがあり、6月の例大祭ごろに花をつけます。
いずれも2025年6月8日、11:30ごろ。





